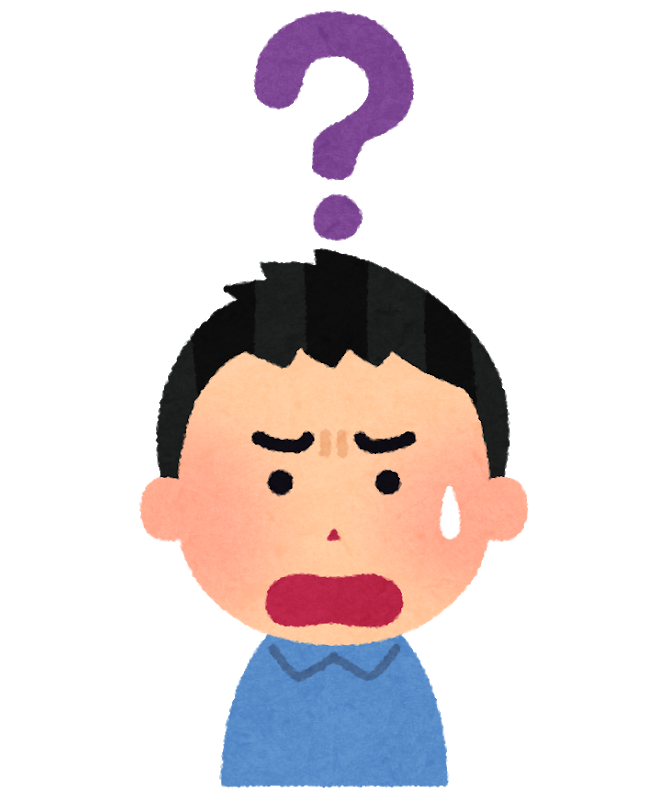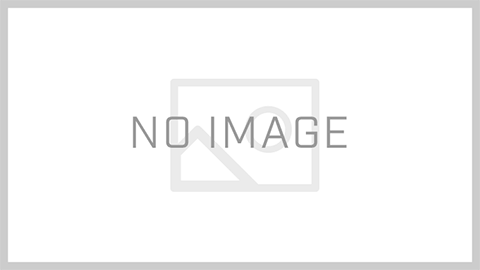本日は、チェーンソーのデプスゲージ調整について解説します。
本記事の内容
● 読んですぐにデプスゲージ調整ができるようになる
● チェーンソーのデプスゲージ調整の方法がわかる
● デプスゲージ調整の応用技がわかる
チェーンソーのデプスゲージ調整の方法を解説【 応用技も教えるよ 】

こんにちは、ゆういちです。
本日は、チェーンソーの目立てとセットで行うデプスゲージ調整について解説します。
デプスゲージ調整も目立て同様にこだわると非常に奥が深いですが、本記事では「デプスゲージ調整をやったことがない人が、とりあえず調整をマスターして不自由なくチェーンソーが使えるレベルになる」を目標に記事を書いていますので、最後までお読み下さい。
デプスゲージ調整とは?
デプスゲージとは、ソーチェーンを構成する部品の1つで、木を切り込む量を調整する重要な箇所です。
チェーンソーの目立てをしていくと、どんどんとカッターが減っていくので、上刃の上側とデプスゲージとの差が、どんどん小さくなってきます。
上刃の上側とデプスゲージの差が0に近づいてくると、研いでも切れない状態になり、逆に差が大きいと刃の抵抗が増してキックバックを起こしやすい状態になります。
では、ちょうど良いデプスゲージの高さはどのくらいなのでしょうか?
ズバリ、0.7mmと言われています。
デプスゲージ調整とは、デプスゲージとカッターの差を約0.7mmに保つことを言います。
デプスゲージ調整に必要な道具

デプスゲージ調整に必要な道具は2つです。
● 平やすり
● デプスゲージジョインター
平やすり
デプスゲージ調整を行うための両面平らなやすりです。
荒い面と細かい面があるので、調整がしやすいです
私は、ハスクバーナ製とオレゴン製の2本を所有して使っています。
デプスゲージジョインター
デプスゲージの高さを均一に調整するための器具になります。
初心者の方は、慣れるまで確実に必要な道具になるのでご用意ください。
オレゴン製の、目立てからデプス調整に必要な道具が1式セットになっている便利キットがお得なので参考までに。
デプスゲージ調整のやり方

デプスゲージ調整は、平やすりでデプスゲージを削っていくのですが、1ミリに満たない調整をするので、肉眼目視だと0.7mmに揃えるのは至難の技です。
これを可能にするのが、先ほど紹介したデプスゲージジョインター。
使い方は簡単、上刃にデプスゲージジョインターを置くと、デプスゲージの先端が画像のようにヒョコっと出て来ます。
この出てきた部分をそのまま平やすりで削ると、約0.7mmに調整できます。
これをソーチェーン1周、全てのデプスゲージの調整をすれば完了になります。
デプスゲージの高さがバラバラだと曲がって切れる原因に
左右のカッターでデプスゲージの高さが違うと、切り込み量に差が出るので、片方に曲がって切れることがあります。
そうならないためにも、デプスゲージジョインターの使用をおすすめします。
原因は他にもありますが、曲がって切れるようであればデプスゲージの調整を確認して下さい。
デプスゲージ調整応用技編
ここでは、私が普段から乱用しているデプスゲージ調整の応用技を紹介したいと思います。
正しい方法ではないので参考程度に。
先ほど「デプスゲージジョインターを使用してデプスゲージの高さを均一にしましょう」と書きましたが、はっきり言って毎回はめんどくさいですよね。(そんなことを言うなw)
私は林業の現場でチェーンソーを使うので、毎回ジョインターを使って調整する時間はないのです。
そこで私が実施している応用編のやり方を紹介します。
慣れればだいたい同じ高さに調整可能です。
平やすりの厚みでデプスゲージの高さを判断する
平やすりをデプスゲージに当てた時に、平やすりのどこに上刃の上側が来るかを見て調整する方法です。
平やすりの厚みがだいたい2.3mmなので、半分よりちょっと下の1mmくらいで調整しています。(針葉樹の間伐作業時)
平やすりを当てる角度で見え方が変わってしまうことがあるので、平行にやすりが当たるように注意して下さい。
この方法で、デプスゲージが高すぎて切れなかったということはないですし、丸太が曲がって切れることもないです。
ジョインターを使わずに、デプスゲージの高さをある程度測れるので、ぜひ試してみてください。
デプスゲージ調整は樹種によって変える話
最後になりますが、少しだけ上級編のお話をしておこうと思います。
チェーンソーの目立てやデプスゲージ調整は、こだわればかなり奥が深いという話をしました。
どう深いかというと、仕事の内容や切る木の種類(樹種)によって刃の研ぎ方やデプスゲージの調整を変えるからです。
例えば、杉の木の間伐作業だったらカッターの角度を若干鋭くして、デプスゲージを削って下げます。
こうすることで、柔らかい杉の木の伐採では刃の食い込みが良くなり、作業効率が上がります。
しかし、同じ調整で硬い広葉樹のケヤキを切るとなると逆に仕事になりません。
ケヤキは硬いので、刃の角度が鋭いと刃持ちが悪くなって切れなくなってしまいますし、デプスゲージも下げているので、抵抗が大きくなり刃が止まってしまいます。
このように木の硬さ(繊維の強さ)によって調整を変えますし、仕事の内容によっても変えます。
例えば、先ほどと同じ杉の木ですが、特殊伐採(高所伐採)のパターンはどうでしょうか?
特殊伐採の場合は、高所作業なので動きや位置(ポジショニング)が制限されます。
そんな中で先ほどの調整だと、刃の抵抗が大きいのでキックバックや切りすぎてしまうリスクがあがります。(疲労も増大)
高所伐採の場合は、私の場合10がマックスの切れ味だとしたら、7〜8くらいの切れ味に調整してます。
これはほんの1例に過ぎませんが、こだわれば本当に奥が深いので面白いです。
ぜひ、あなたも目立て、デプス調整の技術を深めていき自分に合った調整を見つけてみて下さい。
デプスゲージ調整 まとめ
デプスゲージ調整は、軽くみられがちですが目立て同様に非常に重要なのでマスターして下さい。
正しい目立ての方法をマスターしたい方は、こちらをご覧ください。

最後まで、読んでいただきありがとうございました。